オンラインショップを運営する上で避けて通れないのが「送料」の問題。
送料無料にすれば顧客に喜ばれるけれど、利益が圧迫されそう……。
一方、有料配送にすればコストは抑えられるけれど、カゴ落ち(購入直前での離脱)につながるかも……。
実際のところ、「送料無料」と「有料配送」、どちらが利益につながるのでしょうか?この記事では、それぞれのメリット・デメリットを比較しながら、利益面からの最適解を考察します。
1. 送料無料:売上アップの武器になるか?
メリット
- 購入率アップ:心理的ハードルが下がり、購入完了率が向上。
- 客単価が上がる可能性:送料無料ライン(例:5,000円以上)を設定すれば、ついで買いを促せる。
- 広告文として強力:「今だけ送料無料!」という訴求がプロモーション効果を生む。
デメリット
- 送料は結局店舗負担:利益率の低い商品では、送料が重荷になりがち。
- まとめ買いが進まない場合は赤字リスク:単価が低い商品の単品購入では赤字に転落することも。
2. 有料配送:健全な利益を守る手段?
メリット
- 明確なコスト分離:商品価格に送料を含めないため、利益構造がクリア。
- 値引き圧力を避けやすい:送料が別料金であることを前提にすれば、値下げ交渉の余地が少ない。
デメリット
- 購入離脱の原因になる:カートに進んだ瞬間、送料表示で購買意欲が冷めることも。
- 競合と比較されたときに不利に:送料無料が当たり前の市場では、見劣りするリスク。
3. 利益面でどちらが有利か?【ケース別分析】
ケースA:客単価が高い商材(例:家電、家具など)
→ 送料無料の方が有利な場合が多い。高額商品の場合、送料の占める割合が小さいため、店舗が送料を吸収しても十分な利益が残る。さらに「送料無料」による安心感が購買決定を後押し。
ケースB:客単価が低い商材(例:雑貨、小物、食品など)
→ 有料配送の方が健全な利益を出しやすい。商品価格が1,000円程度なのに対し、送料が700円となると、送料無料では赤字必至。対策としては「〇円以上で送料無料」などの条件付き無料化が有効。
ケースC:リピーター重視型のサブスクリプションや定期購入
→ 初回送料無料+継続有料配送などのハイブリッド戦略が◎。まずはお試しで負担を下げ、その後は安定的に収益化する設計が鍵。
4. 最終結論:一律ではなく「戦略的な送料設計」を
「送料無料が利益につながる」とは一概に言えません。重要なのは以下のポイントです:
- 顧客単価と送料のバランス
- 競合との差別化
- リピーター率とLTV(顧客生涯価値)
- 送料をマーケティングの一環と捉える視点
実践アドバイス:
- 「〇〇円以上で送料無料」を設定し、客単価を底上げ。
- 単価が低い場合は「送料込み価格」にして販売ページで“送料無料”をうたう。
- 地域別送料、重量別送料などを活用し、損益を細かく管理する。
まとめ
「送料無料 vs 有料配送」は、単なるコストの問題ではなく、顧客心理・購入率・利益率を包括的に見て決めるべき戦略です。
送料は「かかるもの」ではなく、「使えるもの」。あなたのショップに最適な送料戦略を見つけて、利益最大化につなげましょう!
※本記事の情報は執筆日時点のものです。今後サービス内容や料金等が変更される可能性がありますので、最新情報は各公式サイトでご確認ください。






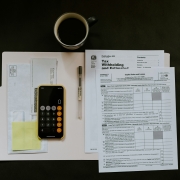



 Japanese Yen Exchange Rate
Japanese Yen Exchange Rate
