~「消費税」では語れない、越境ビジネスに必要な視点とは?~
GST(Goods and Services Tax)は、世界中で採用が広がっている付加価値税(VAT)の一形態。
消費税に似ていますが、ビジネスが「モノやサービスをどこに提供するか」によって納税義務や税率が大きく変わるため、越境ECや国際取引に携わる人は要注意です。
今回は、GSTの仕組みと各国の特徴的なルールをわかりやすくまとめます。
1️⃣ GSTとは?基本の仕組み
GSTは「モノ・サービスに広く課される間接税」で、最終消費者が負担するもの。
しかし実際にはサプライチェーンの各段階で課税され、事業者は「仕入れ時のGST」を差し引いた分を納税します。
🔁 課税と控除の流れ(シンプル例)
- 仕入れ → GST支払う(例:10%)
- 販売 → GST徴収(例:10%)
- 差額を政府に納税(販売GST − 仕入GST)
つまり、中間事業者は実質的な負担はゼロですが、正確な申告と帳簿管理が求められます。
2️⃣ 国ごとのGST/VAT制度:違いとポイント
各国には名称や運用ルールの違いがあるため、グローバル事業者は必ず確認が必要です。
🇦🇺 オーストラリア(GST)
- 税率:10%
- 海外事業者にも登録義務あり(年間売上AUD 75,000超)
- 越境ECにも適用:物理商品でも$1以上なら課税対象
🇸🇬 シンガポール(GST)
- 税率:9%(2024年より)
- 電子サービス提供(SaaS等)でも海外事業者に登録義務
- 非課税対象:金融サービス、不動産の賃貸など
🇮🇳 インド(GST)
- 税率:5〜28%(品目ごとに異なる)
- 中央GST+州GSTの複雑な二重構造
- 登録・納税義務のハードルが高め
🇪🇺 EU諸国(VAT)
- 税率:17〜27%(国による)
- OSS制度により、1国で登録すれば全EUに販売可能
- 越境ECで€10,000以上ならVAT登録が必要(新ルール)
🇳🇿 ニュージーランド(GST)
- 税率:15%
- 海外からのデジタル・物理商品の提供にも課税
- 「low-value goods」制度に注意(NZD 1,000以下の商品はGST即徴収)
3️⃣ 日本企業が直面する実務課題
🧾 インボイスの整備
- 海外では「税額明示」が義務。日本式の請求書では不十分なことも。
🌍 各国での「非居住者登録義務」
- 現地に拠点がなくても、現地税務署に登録が必要なケースが増加中。
🔄 複数国での税務申告フロー
- 国ごとの報告形式が異なるため、会計・ERPの連携が重要。
✅ まとめ:GSTを「コスト」ではなく「戦略」に変える
今やGSTは、単なる税金ではなく、ビジネスの信頼性・競争力に関わる要素。
特にD2Cブランドや越境EC企業にとっては、各国のルールを理解し、適切な登録・申告をすることが市場参入の第一歩です。
💡 豆知識:日本は「GST非導入国」
- 日本では「消費税」という独自制度があるが、国際的にはVAT/GSTが主流
- 今後の越境EC拡大により、日本企業のGST対応は不可避に




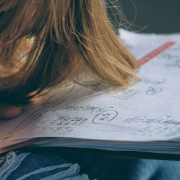






 Japanese Yen Exchange Rate
Japanese Yen Exchange Rate
